
デジタル時代の「確かな安心」を支える - 明治安田内部監査変革への挑戦
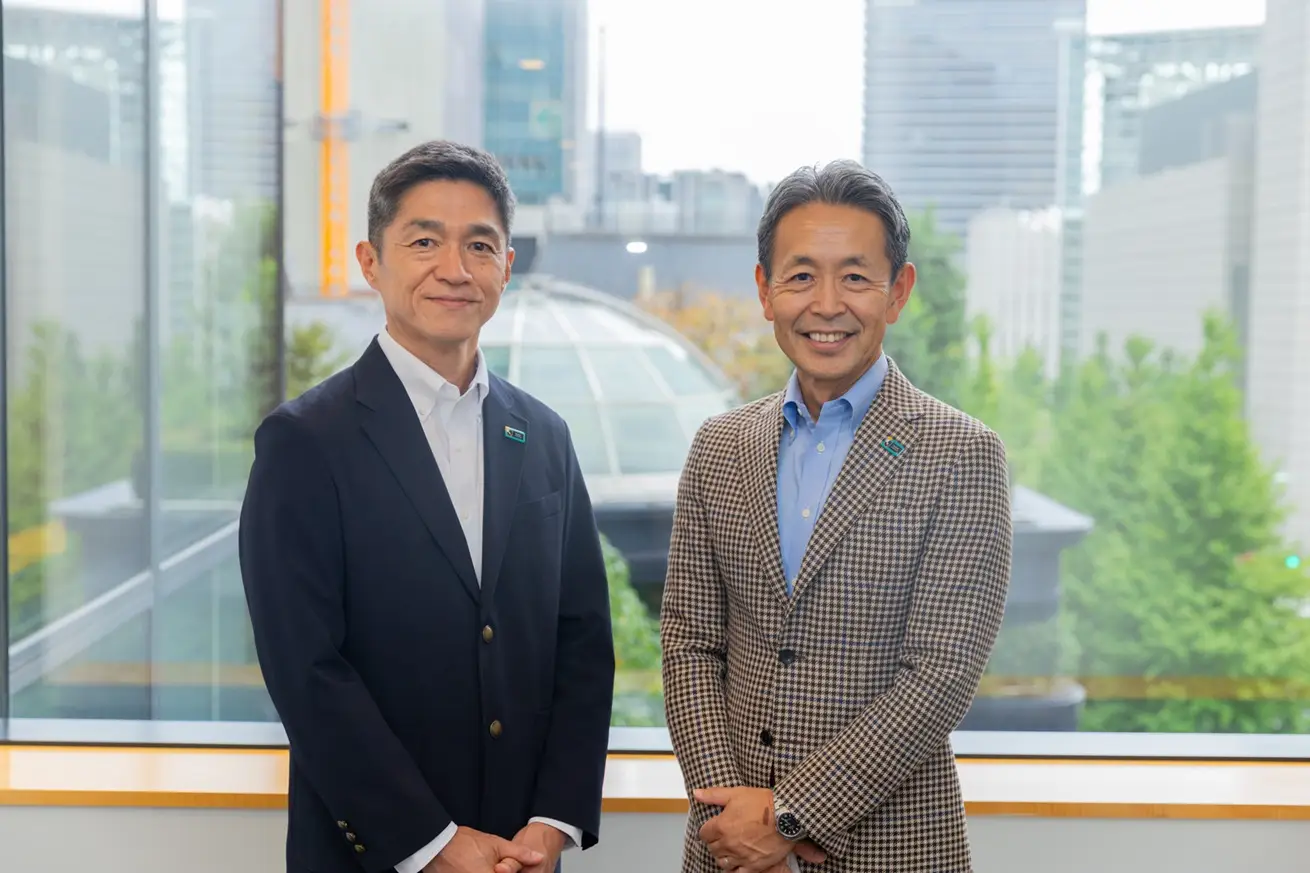
明治安田生命保険相互会社
監査部長 馬場 美仁様(写真右)、上席内部監査役 松木 英男様(写真左)
「確かな安心を、いつまでも」という経営理念のもと、日本の生命保険業界をリードしてきた明治安田※。同社は10年計画「MY Mutual Way 2030」において「人とデジタルの効果的な融合」を掲げ、内部監査の高度化にも積極的に取り組んでいます。今回は、監査部長である馬場美仁様と監査部内のIT/DX担当である松木英男様に、デジタル時代における内部監査の進化と展望について詳しくお話を伺いました。
※2024年度からスタートした3ヵ年プログラム「MY Mutual Way Ⅱ期」では、「生命保険会社の役割を超える」ことをめざしていきます。この言葉には、「保障とアフターフォローの提供」という従来の生命保険会社の役割を大切にしながら、「みんなの健活プロジェクト」「地元の元気プロジェクト」の2「大」プロジェクトの取組みを強化していくことによって、「ヘルスケア・QOLの向上」と「地域活性化」という二つの方向にさらに役割を拡充していく、という強い想いが込められています。これらを必ず実現する、という決意を込めて、ブランド通称を「明治安田生命」から「明治安田」に改めました。
相互会社として歩んできた信頼と革新の道
―まず、明治安田の歴史と特徴について教えてください。
馬場様 当社は1881年に有限明治生命保険会社として創業し、2004年に明治生命と安田生命が合併して現在の明治安田となりました。140年を超える歴史のなかで、約80年にわたり相互会社として、ご契約者の皆さまを「社員」とし、その声を経営に反映させることを大切にしてきました。
私たちの使命は「確かな安心を、いつまでも」という経営理念に集約されています。生命保険という社会インフラを通じて、お客さまの「いざ」という時を支え、さらには健康増進やQOL向上など、生命保険会社の役割を超えた価値創造にも挑戦しています。
現在、2030年までの10年計画「MY Mutual Way 2030」を推進しており、「『ひとに健康を、まちに元気を。』最も身近なリーディング生保へ」の実現に向けて、全社一丸となって取り組んでいます。
―明治安田の強みは何でしょうか。
馬場様 最大の強みは「人」です。全国約3万7000人の営業職員をはじめ、多様な専門性を持つ職員が、お客さま一人ひとりに寄り添ったサービスを提供しています。この「人の力」と、最新のデジタル技術を融合させることで、より高い価値を創造できると考えています。
また、相互会社としてのガバナンス体制も当社の特徴です。ご契約者の代表で構成される総代会を最高意思決定機関としてお客さまご自身の意見や考え方を企業運営に反映させることを可能とし、また、全国の各支社でご契約者にお越しいただき開催するお客さま懇談会を通じて直接的な対話も重視しています。この仕組みが、お客さま本位の経営を支える基盤となっています。
継続的な内部監査態勢の高度化に向けて

―内部監査の高度化に向けた取組みについて教えていただけますか。
馬場様 私たちには忘れてはならない過去があります。2005年に保険金等の不適切な不払いで行政処分を受けた経験です。当社では、この未曾有の事態への対応を通じて、内部監査の重要性を改めて認識しました。
この経験を教訓として、私たちは内部監査態勢の抜本的な改革に取り組んできました。
内部監査の実効性を確保するため「グループ内部監査基本方針」を定め、執行部門から独立した体制を確保したうえで、国際監督規制の強化を見据えたグループベースでの監査部のいっそうの役割発揮に向け、リスクベースかつフォワードルッキングな視点により、内部監査態勢の整備・高度化を進めるとともに、内部監査品質の維持・向上にも努めています。
現在では、リスクベースの監査計画を策定し、データ分析を活用した監査を推進しつつ、カルチャー監査、アジャイル型監査など、さまざまな手法にも取り組んでいます。
2024~2026年の期間に特に注力すべきと考えているのは「Basics & Progress」、つまり基本の維持と不断の進化です。内部監査の基本的な役割を確実に果たしながら、常に新しい手法や技術を取り入れ、進化し続けることが重要だと考えています。
―具体的にはどのような監査手法を導入されているのでしょうか。
馬場様 まず、カルチャー監査についてですが、これは組織風土やリスクカルチャーを評価する新しいアプローチです。経営と営業拠点における行動様式のギャップ等の検証視点、インタビュー・アンケートの対象や質問の設定等、試行錯誤しながら取り組んでおります。
また、アジャイル型監査にも取り組んでいます。従来の監査に比して、リスクの高い検証視点から早期に意見交換可能であること、短期間での検証・見直しを重ねることでリアルタイムに近いアシュアランスの提供が可能であること、効率的な内部監査運営により所要時間を短縮可能であるなどの利点があると考えており、いっそうの定着に向けたノウハウの蓄積を進めてまいります。
グループ内部監査の観点では、国内の主要なグループ会社に設置している内部監査部署に対して指導・助言等を行なうほか、海外保険グループ会社とも適宜連携するなど、グループとしての内部監査態勢の強化にも努めています。
生成AIとデータ分析が拓く監査の新地平

―デジタル技術の活用について教えてください。
松木様 当社は「MY Mutual Way 2030」の重点方針として「人とデジタルの効果的な融合」を掲げており、内部監査においても積極的にデジタル技術を活用しています。
特に生成AIの活用は、内部監査の在り方を大きく変える可能性を秘めています。現在、AIをアシスタントとして監査プロセス全般に活用する取組みをスタートさせています。例えば、個別監査におけるリスク評価や監査上の着眼点の検討にAIを活用することで、多くの資料やデータのなかからフォーカスすべきポイントを効率的に抽出することが可能になりました。
また、会議の議事録作成や各種監査文書の作成のサポートにも活用し始めています。これにより、監査人はより付加価値の高い分析や洞察に時間を割けるようになってきています。
―AIの活用における課題や留意点はありますか。
松木様 もちろん、AIは万能ではありません。特に内部監査においては、高度な判断や複雑な状況の理解が求められる場面が多く、これらは依然として人間の専門性に頼る必要があります。
重要なのは、AIと人間の役割を適切に分担することです。AIには資料やデータの一次分析や定型的な文章作成を任せ、人間は戦略的な判断や複雑な問題の解決、そして被監査部署とのコミュニケーションに注力する。この協働により、監査の効率性と有効性の両方を高めることができると考えています。
また、生成AIの活用にあたっては、ハルシネーションのリスクや情報セキュリティの確保など、特有の課題への対応も必要です。監査人自身がAIの仕組みや限界を理解することも重要で、部内でAIリテラシー向上のための研修も実施しています。
専門性と多様性を重視した人財育成戦略

―内部監査人財の育成についてはどのような取組みをされていますか。
馬場様 内部監査の質は、結局のところ「人」で決まります。そのため、人財育成には特に力を入れています。
まず、専門資格の取得を積極的に支援しています。CIA(公認内部監査人)、CISA(公認情報システム監査人)、CFE(公認不正検査士)などの資格取得を推奨し、受験費用の補助や勉強会の開催など、組織的なサポート体制を整えています。実際に、監査部の過半のメンバーが必要な資格を取得しており、専門性の向上に努めています。
また、日本内部監査協会のCIAフォーラム研究会にも積極的に参加し、他社の内部監査部門との交流を通じて最新の知見を取り入れています。業界全体の内部監査の発展に貢献することも、私たちの重要な使命だと考えています。
―デジタル人財の育成についてはいかがでしょうか。
馬場様 当社では、全社的にデジタル人財の育成に力を入れています。単にツールを使える人材ではなく、デジタル技術を活用して業務変革を主導できる人材の育成をめざしています。
内部監査部門においても、データ分析やAI活用のスキルを持つ人材の育成が急務です。従来の監査スキルに加えて、プログラミングやデータサイエンスの知識も必要になってきています。このため、外部研修への派遣や内部監査部門内での研修、実務を通じたOJTなど、多様な育成プログラムを展開しています。
特に生成AIについては、その可能性と限界を正しく理解し、適切に活用できる人材の育成に注力しています。AIを活用した監査手法の開発や、AIツールの評価・選定など、専門的な知識とスキルが求められる領域が増えています。
3ラインモデルで実現するリスク管理の実効性向上

―リスク管理体制について、3ラインモデルの導入状況を教えてください。
馬場様 当社では、内部監査を、組織体の目標の達成に資することを目的に、公正かつ客観的な立場で組織体の活動の遂行状況を評価し、助言・提言等を行なう重要なプロセスと位置づけており、その実効性を確保するため「グループ内部監査基本方針」を定めています。同方針に基づいて、指名委員会等設置会社において設置が必須である監査委員会の直属の組織として監査部を設置しているほか、同方針等の改正や内部監査計画の策定等は監査委員会の決議事項とすること、内部監査の結果を監査委員会に報告することなどにより、執行部門から独立した体制を確保しています。
内部監査部門は第3線として、第1線、第2線から独立した立場で、リスク管理態勢全体の有効性を評価しています。重要なのは、単に問題を指摘するだけでなく、建設的な改善提言を行ない、組織全体の価値向上に貢献することです。
また、「内部監査計画」を「監査委員会監査計画」の重点監査項目の具体的計画として位置付けるなど、法定の監査委員会監査との連携も重視しています。それぞれの監査主体が情報を共有し、監査の重複を避けながら、全体として監査の実効性を高めています。
未来に向けた内部監査のビジョン

―最後に、内部監査部門の今後の展望をお聞かせください。
馬場様 私たちは、2024~2026年度において、「リスクベース監査の実践と経営戦略を支える内部監査の推進~Basics and Progress(基本の維持と不断の進化)~」をめざす姿としています。準拠性監査を法令面だけでなくプリンシプル、ガバナンス・コード、社会規範等も含めた広範なものと整理し、準拠性監査、リスクベース監査、経営監査、3つ視点のバランスに留意をした内部監査計画を策定しています。
そのために、継続的な監査(Continuous Auditing)の実現に向けて取り組んでいます。生成AIを活用したリアルタイムのリスクモニタリングにより、問題が顕在化する前に予防的な対応を可能にする。これがデジタル技術を活用した次世代の内部監査の姿だと考えています。
生成AIについては、監査計画の策定から、リスク評価、監査の実施、報告書作成まで、監査プロセス全体での活用を検討しています。例えば、過去の監査結果やリスク情報を学習させることで、より精度の高いリスク予測や監査ポイントの提案が可能になると期待しています。
また、ESGやサステイナビリティの観点からの監査も重要性を増しています。企業の社会的責任を果たしているか、持続可能な経営が行なわれているかという視点での評価も、内部監査の新たな役割となっています。
―フロンティアとの協業についてはいかがでしょうか。
馬場様 フロンティア様とは、特に内部監査における生成AI活用分野で協業を行ない、個別監査への帯同を通じてさまざまな角度からアドバイスをしてもらい、大変感謝しています。
生成AIは急速に進化している分野ですので、最新の技術動向やベストプラクティスを取り込むことが重要です。フロンティア様からは、生成AIを活用した監査プロセスへの変革、AIツールの動向把握、さらには生成AI特有のリスクの識別など、実践的なアドバイスをいただいています。
例えば、生成AIを監査業務に適用する分野の識別やプロンプト設計、AIの出力結果の調整方法、ハルシネーション対策など、実務で直面する課題について具体的な解決策を提示していただいています。このような専門的な知見は、私たちが安全かつ効果的に生成AIを活用していく上で非常に貴重です。
今後も、さまざまな外部の専門家の知見を積極的に取り入れながら、AIを活用した次世代の内部監査を実現していきたいと思います。内部監査を通じて「確かな安心を、いつまでも」お届けできるよう、これからも努力を続けてまいります。
―本日は貴重なお話をありがとうございました。

■インタビュー時期:
2025年10月※文中の会社名・役職等は取材当時のものです。
会社名称 明治安田生命保険相互会社
事業内容 国内大手の生命保険会社。個人および法人向けに多様な保険商品や資産運用サービスの提供を行う。
URL https://www.meijiyasuda.co.jp/







